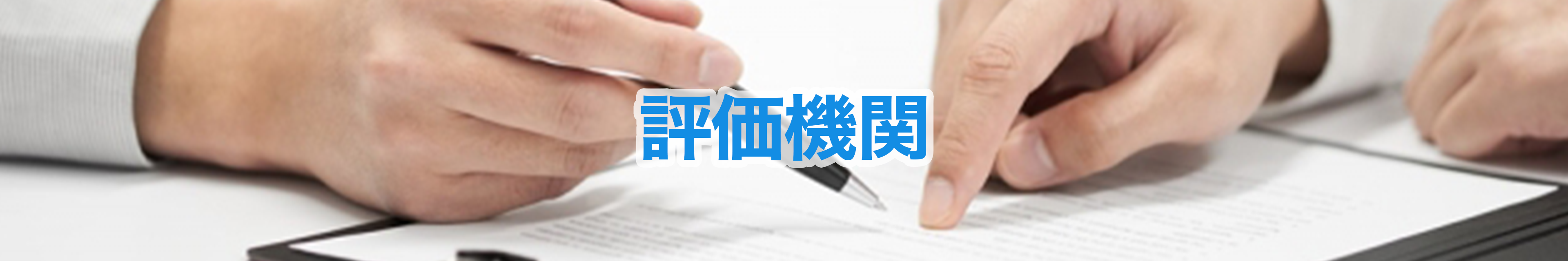
評価機関の方へのお知らせ
| 【重要】令和7年度 京都介護・福祉サービス第三者評価新規受診応募 受付開始について | 25年4月10日掲載 |
評価情報を追加した直近の事業所・施設
| 新着 | 保育施設 | 千代川こども園 一般社団法人 京都府保育協会 |
| 新着 | 保育施設 | 上賀茂こども園 一般社団法人 京都府保育協会 |
| 新着 | 保育施設 | 幼保連携型認定こども園 なごみこども園 一般社団法人 京都府保育協会 |
| 新着 | 保育施設 | 永福こども園 一般社団法人 京都府保育協会 |
| 新着 | 保育施設 | 亀ヶ丘保育園 一般社団法人 京都府保育協会 |
介護 福祉 社会的養護 より多くを一覧でみる より多くを一覧でみる
事業所の検索
第三者評価サイトに登録されている受診事業所・施設を語句検索できます。現在、1635の事業所や施設が登録されています。
検索語句の例:「法人の名称」「事業所・施設の名称」「所在地の地名」など
語句をスペースで区切って複数入力すると ‘OR検索’ できます。
条件検索
条件検索するには下の検索をご利用ください。
ひとつの条件内を複数チェックすると ‘OR検索’ になります。(例:「京丹後市」「宮津市」のいずれかを含む)
「エリア」に「サービス分類」を追加した場合など、条件をまたがる場合は、‘AND検索’ になります。(例:「エリア」「サービス分類」の条件をいずれも満たす)
次のコンテンツはこのページのURLを、クリップボードへコピーするためのユーティリティエリアです。クリップボードへコピーするためのボタンがあります。
ボタン、
URLをコピーしました。
このページのURLは、https://kyoto-hyoka.jp/評価機関の方へ/です。